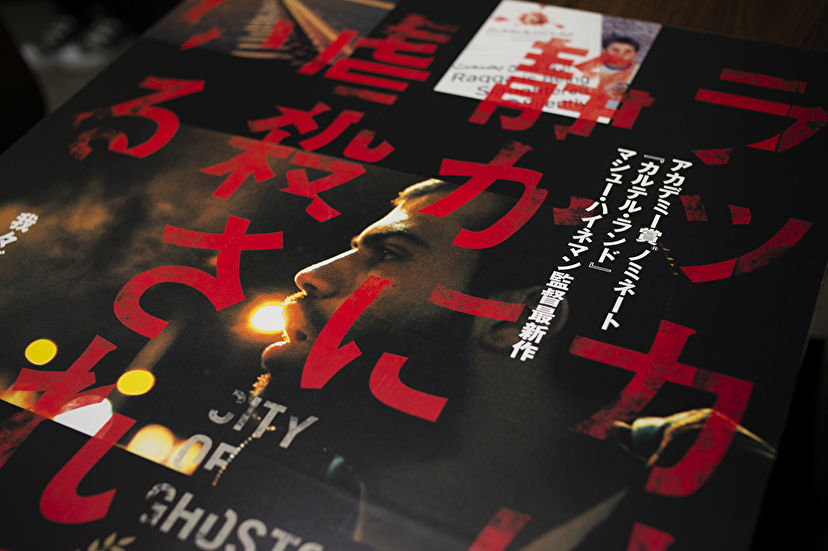ある3月の午後。関西学院大学のキャンパスでは、学生たちがバドミントンに興じ、小さな子ども連れの家族がのんびりと過ごしていた。シリア人留学生のイーサーさん(33)はキャンパスの一室で話し始めた。「家のすぐそばで爆発がありました。数えきれないほど。友人もたくさんけがをした。亡くなった人もいます」。恐怖は今も体から離れない。内戦開始から7年。故国での死者は35万人を超え、難民は560万人に達する。そんな中、日本政府は大学院留学生に限ってシリア人の受け入れを始めている。イーサーさんも日本に暮らす「難民留学生」の一人だ。故国を離れても「自由」はなお遠いという、その実態、その思いとは……。折しも、この4月中旬には米軍などによるシリア攻撃が始まった。(末澤寧史/Yahoo!ニュース 特集編集部)
「シリア難民留学生」来日
昨年7月に来日したイーサーさんは大学院の経営戦略研究科に在籍し、経営学修士(MBA)の取得を目指している。33歳。「名前を公表しない」という条件付きの取材で、「イーサー」は仮名である。

自習室でパソコンに向かうイーサーさん(撮影:笹島康仁)
イーサーさんは首都にあるダマスカス大学を卒業後、同大学の経理担当職員として働いていた。ところが、ダマスカスの東部では、2012年ごろから政権軍と反体制派武装組織の間で激しい戦闘が続くようになる。
「家のすぐそばで数えきれないほど爆発がありました。けがを負った友人もたくさんいました。亡くなった人もいます……。どっち側の攻撃か? どこから(爆弾が)飛んできたかなんて分かりませんよ」
2013年に入ると、彼は隣国レバノンの首都ベイルートへ脱出する。レバノンは人口約400万人で、国土は岐阜県ほどの広さしかない。当時はそこに、100万人超のシリア人が難民となってなだれ込んでいた。イーサーさんは先に避難していた兄らを頼り、歯科関係の会社に職を得たという。

「故郷の町からタクシーでベイルートまで避難しました」とイーサーさんは言う(撮影:笹島康仁)

レバノンのシリア人難民キャンプにあるUNHCRの難民登録センター=2013年12月(ロイター/アフロ)
日本政府の留学生の募集を知ったのは、レバノンへ逃れて3年後の2016年11月。UNHCR(国連難民高等弁務官事務所)からの情報だった。
「日本留学はチャンスでもあったけれど、ほかに選択肢がありませんでした。レバノンはアラブの同胞ですから、大量の難民を受け入れていました。それでも、差別とは言いませんが、次第にレバノン政府の規制や(難民に対する)国民感情が厳しくなって……。自分で打開策を見つけるしかない状況だったんです」
日本政府がシリアから「難民留学生」の受け入れを始めたのは、2017年度になってからだ。公式表明は、2016年5月の「伊勢志摩サミット」。欧州に100万人超のシリア難民が押し寄せ、国際社会では「シリア難民をどうするか」が大きなテーマになっていた。
日本政府の計画では、国際協力機構(JICA)の「技術協力制度」や文部科学省の「国費外国人留学生制度」枠を利用し、5年間で最大150人のシリア人留学生を受け入れる。イーサーさんも技術協力制度で来日した一人だ。

関西学院大学西宮上ケ原キャンパスの中庭(撮影:笹島康仁)
語ることへの「不安」
実は、イーサーさんにたどり着くまでに、多くのシリア人が取材を拒んだ。「何かあったら不安」と言い、いったん引き受けた後で断った人もいる。イーサーさんの取材に際しては、JICAと大学の広報を通し、「匿名でなら」の条件が付いた。
日本に来てなお、なぜ、シリアの人々は自由に語れないのか。シリア社会に詳しい考古学者の山崎やよいさんは「政権への疑心暗鬼があるからです」と言う。
「自由に発言すると、パスポート更新に影響があるかもしれない。家族に危害が及ぶかもしれない。可能性の問題ではありますが、不安にさせる状況自体がシリアのいびつさを表しています」

考古学者の山崎やよいさん。シリア在住20年以上。帰国後の現在は仲間と団体をつくり、シリアの手芸品の販売を通じてシリア人女性の自立を支える(撮影:笹島康仁)
「アサド独裁」が長く続くシリアでは、内戦前から政治活動や表現の自由の制限、拷問などが続き、国際人権団体などが厳しい非難を続けている。その政権に対抗する国民の蜂起。内戦のきっかけとなったその蜂起から間もない2011年3月下旬、山崎さんはシリアにいた。
「シリアの人たちは、何よりも表現の自由がほしかったのではないでしょうか。チュニジアやエジプトで革命を起こした(民衆蜂起の)『アラブの春』を見て、(自分たちも)できるのではないか、と。民主主義を経験してみたかったんだと思います」
しかし、シリアに「アラブの春」はやってこなかった。
国際NGO「シリア人権監視団」のこの3月の発表によると、シリア内戦の死者は35万人以上に達する。UNHCRによれば、この4月7日時点で、国外に逃れたシリア難民は約560万人。内戦は現在、ロシアの支援を受けたアサド政権が軍事的な優位にあるが、この4月になって米軍などが軍事攻撃に踏み切るなど戦闘終結のめどは立っていない。

地中海へ脱出したシリア難民たち(ロイター/アフロ)

山崎さん(中央)は、シリアのアレッポ大学で考古学を教えていた。写真は2003年(本人提供)
「ほぼ毎日ミサイルが。でも比較的安全でした」
医師のアーセム・マンスールさん(27)はシリア北部のアレッポ大学を卒業後、文科省の国費留学生枠を使って来日した。「難民枠」が始まる2年前、2015年のことだ。当初は2011年に慶應義塾大学に留学する予定だったが、内戦が始まり断念した経緯もある。
「もともと父の留学や仕事の関係で、日本で生まれ、9歳まで育ちました。そんな背景と、先端的な医療も学べるので、日本に留学したんです」
東京大学大学院医学系研究科の博士課程に在籍し、神経内科の遺伝疾患を研究している。
「難民枠」ではなかったとはいえ、マンスールさんの過酷な体験は他のシリア人と変わりない。アレッポも激戦地となった。

アーセム・マンスールさん。東京大学医学部附属病院内の実験室で遺伝疾患を研究する(撮影:笹島康仁)
「アレッポの東部は戦闘が激しく、ほぼ毎日頭上をミサイルが飛んでいました。大学の寮に3万〜4万人も避難民が押し寄せて……。私はシリア赤新月社の医療ボランティアもしていました。たくさんの医師が危険を顧みず救助活動に従事し、その中で多くの友人が命を落としました。薬を買えない貧しい人は多いし、薬も足りない。悲惨でした」
自宅の周辺でも、来日までの4年間に4回爆発があった。それでもシリア政府の支配下にあり、「比較的安全」な地域だったという。
シリア難民をどうすればいいのか。マンスールさんの希望はシンプルだ。各国は受け入れをもっと拡大してほしい、と。
「シリア難民は、人道問題、国際社会の問題です。私も友人と戦災孤児の支援を続けています。留学生という形であれ、受け入れはとても重要です。教育を受けた難民は、いずれ働き、社会に貢献できる存在になります」

2014年、医師国家試験の終了後にアレッポ大学病院の前で同期と。右から3人目がマンスールさん(本人提供)

シリアにいたころのマンスールさん(右端)と弟たち(撮影:笹島康仁)
“難民を難民として受け入れない”日本
法務省によると、2017年の難民認定申請者数は1万9628人だった。それに対し、認定者数は20人。シリア人に限ってみると、2011年以降、難民申請は計81人で、認定はわずか12人だ。UNHCRによれば、「難民危機」と言われた2015年末時点で、ドイツは11万6000人、スウェーデンは5万3000人のシリア難民を受け入れている。日本は非常に少ない。これらは「難民条約」に基づいて法務省が所管する「難民認定制度」上のデータであり、JICAや文科省が主導する、イーサーさんのような「難民留学生」は含まれていない。それらを含めても少ないと言える。
ただ、シリア人に限らず、日本政府はそもそも、これまでも現在も、難民の受け入れに消極的だ。こうした現状を関係者はどう見ているのだろうか。
東京・四谷にある難民支援のNPO「難民支援協会(JAR)」を訪ねた。応対してくれたのは、折居徳正さん(49)。海外での人道支援活動の経験も豊富な難民支援のベテランだ。

地中海でNGOに救助されたシリア難民の女児=2016年8月(ロイター/アフロ)
同協会は2017年4月、民間として日本初の難民受け入れプログラムをスタートさせた。日本語学校に通いながら大学進学をめざすプログラムが中心で、渡航費は寄付金で賄い、日本語学校の授業料は無料、生計はアルバイトで立てる、という枠組みだ。
難民条約などに基づく「難民認定」であれば、受け入れ側の国民と同じ権利が保証され、定住に向けての公的支援も受けることができる。
協会のこのプログラムは違う。「人道配慮」によって「留学生」としての在留資格をもらった上で、日本語学習や就労など定住に向けての支援は「民」の力でやっていこう、という狙いだ。
折居さんは「(民間による難民の)受け入れは国際的にも拡大しています。私たちは日本での先行モデルをつくり、政府の受け入れ拡大も促したい」と言う。昨年度はトルコに逃れていた6人のシリア難民をこの制度で日本に招くなど、少しずつ実績を重ねている。

乗っていた船を脱し、陸に向かって泳ぐシリア難民たち=2015年9月(ロイター/アフロ)
同協会の広報担当、田中志穂さん(41)はこう言う。
「本当は、難民を難民として受け入れないことには無理があります。日本の移民受け入れも同じです。(正式には移民を受け入れていないのに)サイドドアをたくさん開けて、実質的に移民を受け入れてきました。それは外国人を労働力としてしか見ていないからでもある。その人が老いて、死んでいくという当たり前のことを想定した受け入れ態勢になっていないんです」
ボランティア頼りの外国人定住支援
こうしたなか、「難民」とされず、慣れない日本で暮らすシリアの人たちもいる。
サミア・アルイマムさん(39)は、兵庫県三木市に住む。中古車部品の貿易をする夫(46)の呼び寄せで、4人の子どもとともに2015年に来日した。内戦の激しさがピークに達していた頃だ。

「ヤード」と呼ばれる解体作業場。三木市にはパキスタンやシリアなど多国籍の14社が集まるという(撮影:笹島康仁)
彼女はシリアの大学で土木工学を学び、卒業後は首都で建物の設計などを手がけていた。三木市に来てからは働いておらず、宗教上の理由で日本の学校給食などを口にできないわが子のために食事を作って過ごす日々だという。
「人道配慮」により1年更新で滞在が許可されている。しかし、日本の難民認定は厳しいため、難民申請は諦めている。
「家族の数も多いので、本当は経験を生かして働きたいのですが、就労ビザは取れません。自分のビザ(特定活動ビザ)には就労の制限があります。週28時間以内で、仕事の内容も翻訳やアラビア語講師などに限られています」

サミア・アルイマムさん。「顔を撮影しない」という条件で取材に応じた(撮影:末澤寧史)
三木市には、中古車などの解体業に関わるシリア人が多く集まる。紛争の激しくなった2015年以降、シリア人は増加を続け、現在は40人超。アルイマムさんと同様、ほとんどの人は法的な「難民」ではなく、生活に困難を抱えているケースも多いという。
そうした一部のシリア人住民に対し、三木市国際交流協会は生活情報の提供や日本語教室などを続けている。事務局長の河越恭子さんは「男性には仕事の人間関係があります。でも、女性には日々集う場所、人と交流する場所がない。子どもの学校や病気の対応など日本での生活は男性より大変です」と語る。
日本語の習得を支援するのは、主にボランティアたちだ。
「以前、視察したときに目の当たりにしたんですが、アメリカでは第二言語として英語を学ぶ移民に対してその学習を専門的に支援する公的な仕組みがあるのですね。日本の現状は比較になりません」

三木市国際交流協会の交流イベント。語学教室で学ぶ外国人らが発表を行う。右から4人目の男性はシリア人で、市内に解体作業場を持つ(撮影:笹島康仁)
大学院修了後は、シリアに帰りたい。だが…
難民認定の有無にかかわらず、日本には既に多くの「難民」が暮らしている。
この4月に新学期を迎えた関西学院大学の留学生イーサーさんは「日本は英語の案内も多く、外国人でも住みやすい」と言う。日本での生活にも慣れつつある。気がかりなのは、故郷に残る両親や妹、家族のことだ。
大学院修了後の進路を問うと、「シリアに帰りたい」と即答だった。そんなのは当たり前でしょう、と言いたげでもあった。だが、本当の進路はまだ決めようがない。
「今のシリアは、私にもよく分からない。とても複雑な情勢です。外国の介入が事態を複雑にしているのです」

関西学院大学大学院で学ぶイーサーさん。本当は故国に帰りたい(撮影:笹島康仁)
末澤寧史(すえざわ・やすふみ)
ライター・編集者。1981年、札幌市生まれ。慶應義塾大学法学部卒。2006年から1年間、トルコ共和国のボアジチ大学大学院に留学。シリア滞在経験もある。共著に『東日本大震災 伝えなければならない100の物語⑤放射能との格闘』(学研教育出版)、『希望』(旬報社)、『@Fukushima 私たちの望むものは』(産学社)。
[写真]撮影:笹島康仁、末澤寧史
提供:アフロ、山崎やよいさん、アーセム・マンセールさん
[取材・文]末澤寧史