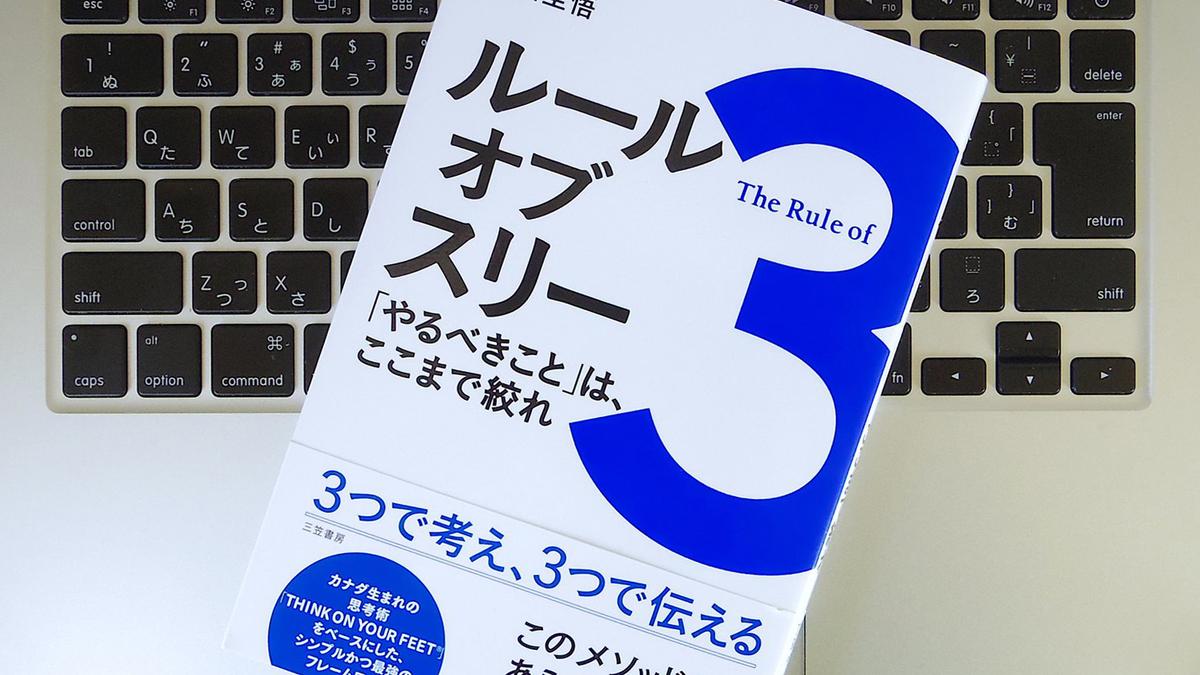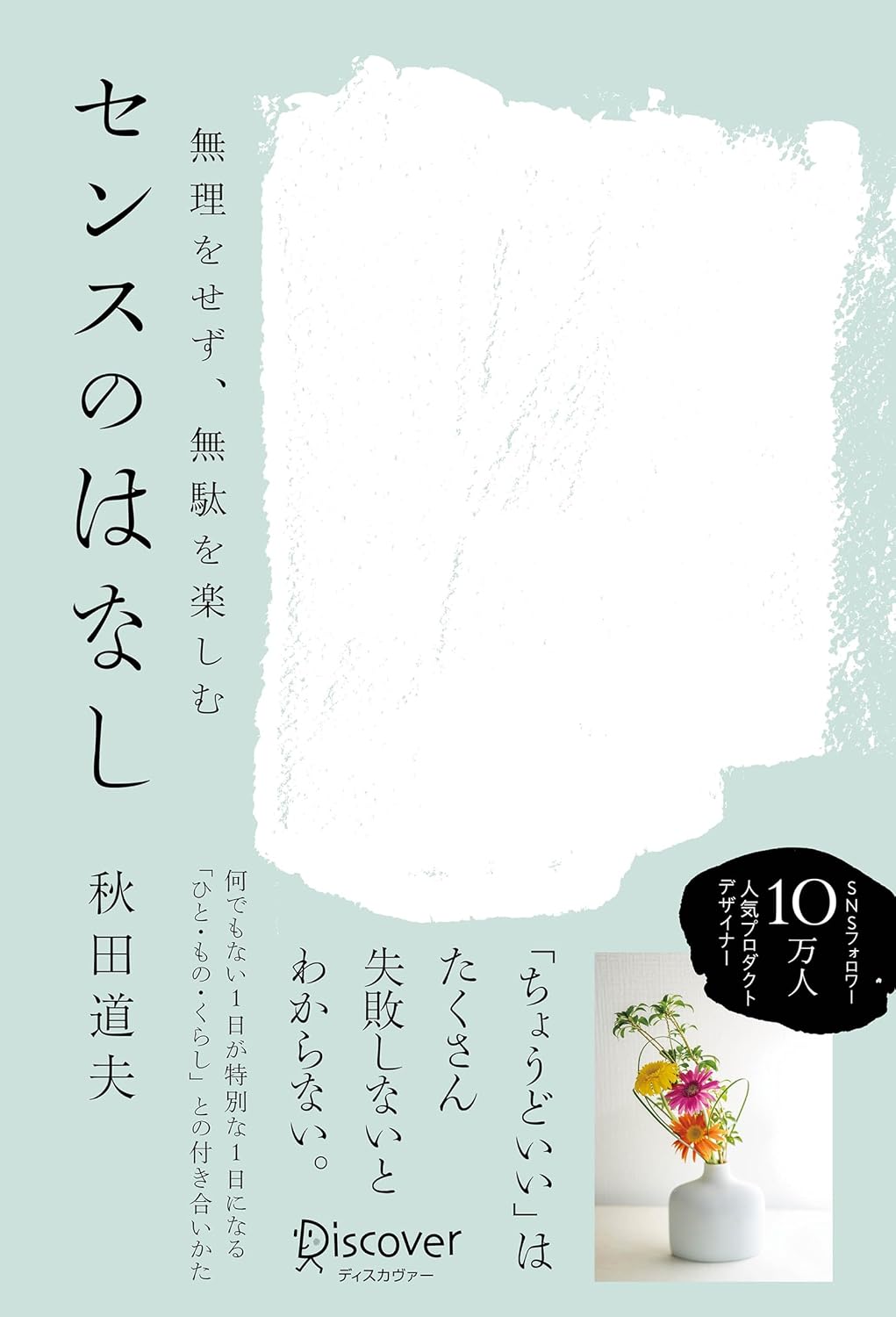ルール・オブ・スリーは直訳すると「3の法則」。これは、考えを「3つ」で整理する、そして、その考えを誰かに伝えるときも「3つ」で伝える、という極めてシンプルなコンセプトを表現する言葉です。(「はじめに」より)
『ルール・オブ・スリー 「やるべきこと」は、ここまで絞れ 』(高田圭悟著、三笠書房)の著者は、こう解説しています。
情報があふれ、複雑化した現代に即した思考法として思い浮かぶのは「論理思考(ロジカルシンキング)」です。しかし時間をかけて考えられないケースも多いだけに、これは必ずしも万能ではありません。むしろビジネスにおいては、素早く考えを整理し、その考えを相手にわかりやすく伝えなければならない場合のほうが多いはず。
そこで役立つのが、「ルール・オブ・スリー」だというのです。「3つで考える」「3つで伝える」だけですが、効果は絶大なのだとか。プレゼンテーションの名手として知られるスティーブ・ジョブズも、多くのスピーチにおいてルール・オブ・スリーを使っていたのだそうです。なぜなら要点を3つに絞ることで、わかりやすく、なおかつインパクトのある形で考えを整理し、発信することができるから。
また、営業や交渉、企画立案、マネジメントなど、あらゆるビジネスシーンで使える手法なのだか。2章「『3つで考え、3つで伝える』基本テクニック ——『やるべきこと』を、ここまで絞る」」で、その基本を確認してみましょう。
「ルール・オブ・スリー」の基本プロセス
「3つのキーワードを決める」
↓
「そのキーワードに肉づけする」
(59ページより)
このように、「ルール・オブ・スリー」のプロセスはとてもシンプル。たとえば、スポーツメーカーが従来にない素材を使用した高機能ランニングシューズを開発・販売することになり、そのシューズのアピールポイントを決めることになったとします。そんな場合は、
1. 機能
2. 特徴
3. メリット
(59ページより)
という3つをキーワードにすることにすれば、あとは肉づけしていけばいいだけ。
1. 機能——シューズのソール部分に、これまでにない反発性能をもたらす新素材を使用。軽量化と同時に、これまでにない高いクッション性を実現している
2. 特徴——高いクッション性が足の前方への振り出しを促し、リズミカルな足の回転を持続させる。また、ヒザへの負担を極限まで抑える効果があり、ハードなトレーニングにも耐える
3. メリットーー上級者にはレースにおける自分のタイムの更新を、ビギナーには走る喜びをもたらす
(60ページより)
短い時間で素早く考えるということについては、「きちんと考えたことにならないのではないか?」という疑問を抱いても当然かもしれません。しかし、短い時間で考えたものの質が悪いということはなく、時間をかければよいというものでもないのだといいます。(58ページより)
テクニック1.——5W1H
キーワードを決めるテクニックとして重要なのが、5W1Hなのだとか。
WHO(誰)
WHAT(何)
WHERE(どこ)
WHEN(いつ)
WHY(なぜ)
HOW(どのように)
(65ページより)
のなかから、「これだけは、言わなければならないこと」を3つ選ぶわけです。たとえば営業マンが「自社製品をどう説明するか」考えるときであれば、
1. WHAT→どのような商品・サービスか
2. WHO→誰に向けた商品・サービスか
3. WHY→なぜその商品・サービスをおすすめしたいのか
(66ページより)
という3つをキーワードにすれば、コンパクトかつしっかりした骨格の内容を準備できるわけです。(64ページより)
テクニック2.——「側面・立場・時・場所」のフレームワーク
カナダのキース・スパイサー博士が「よい考えを、うまく表現できるように」との想いから開発した、「THINK ON YOUR FEET®︎」(即興で考えを整理し、発信するという意味のイディオム)という思考術があるそうです。
「側面」のフレーム What
「立場」のフレーム Who
「時」のフレーム When
「場所」のフレーム Where
(71ページより)
というフレームから3つのキーワードを設定し、考えを整理して、発信していくというもの。
「側面」のフレームからの3つのキーワード
まず「側面」のフレームから3つのキーワードを導き出す方法は、「5W1H」の「WHAT」に当たる部分。「新製品のリリースにあたって、どのような切り口で商品説明をするか?」ということについて考えるのであれば、
1. 特徴
2. 品質
3. 価格
(72ページより)
といった3つの「側面」からキーワードを決めるわけです。たとえば、
心/技/体
品質/コスト/納期
利益/効率/コンプライアンス
素直さ/粘り強さ/集中力
特徴/メリット/デメリット
など。(73ページ「『側面』からの3つのキーワード例」より抜粋)
「立場」のフレームからの3つのキーワード
次に「立場」のフレームから3つのキーワードを導き出す方法は、「5W1H」の「WHO」に当たる部分。「社内コミュニケーションをよくするためには?」ということについて考えるのであれば、
1. 上司
2. 同僚
3. 部下
(74ページより)
といった3つのキーワードで整理し、
産/官/学
自社/競合他社/顧客
先輩/同期。後輩
本部長/副部長/事業部長
新入社員/メンター社員/上司
などを導き出すということ。(75ページ「『立場』からの3つのキーワード例」より抜粋)
「時」のフレームからの3つのキーワード
これは、「5W1H」のうちの「WHEN」にあたる部分。「今後の仕事の活動方針はどうするか?」ということについて考えるのなら、
1. 今年
2. 来年
3. 3年後
(76ページより)
というように、時間軸上の3つのキーワードで整理し、それぞれの時点でどのような活動をするか考えていくのもひとつの方法。
企画/設計/製造
計画/実行/確認
昨日/今日/明日
午前/午後/夕方
入室/面談/退室
などを導き出すわけです。(80ページ「『時』(時点)からの3つのキーワード例」より抜粋)
ちなみに、少し長い「期間」をキーワードにすることも可能。
「場所」のフレームからの3つのキーワード
これは、「5W1H」のうちの「WHERE」にあたる部分。「国」「都市」「地域」など地図上の地名をキーワードにする方法と、「目に見えるところ」をキーワードにする方法の2種があるそうです。たとえば「各地での商習慣の違い」について「地名」で考えるのであれば、
1. 東京
2. 大阪
3. 名古屋
(82ページより)
といった3つのキーワードで整理し、それぞれの場所についての内容を肉づけしていくわけです。
日本/中国/韓国
銀座一丁目/銀座二丁目/銀座3丁目/
日本海側/太平洋側/オホーツク海側
アメリカ/ロシア/中国
東北/関東/近畿
などを導き出すわけです。(85ページ「『場所』(地名)からの3つのキーワード例」より抜粋)
スペースの都合もあって部分的にしかご紹介できませんが、本書ではこのように「ルール・オブ・スリー」の活用法を克明に、わかりやすく紹介しています。仕事を効率的に進めるためには、読んでおくべき一冊だといえそうです。