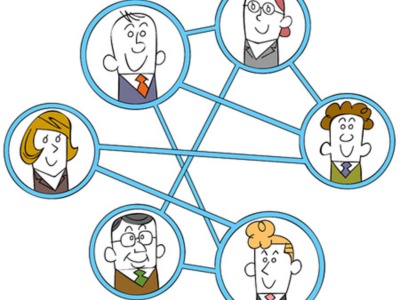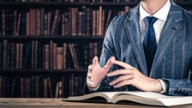日本のビジネス社会おいて「一を聞いて十を知る」は、できる人の代名詞のような使われ方をしています。果たしてそれは本当でしょうか? それは時と場合による、というのが正解と言えます。
上司が部下に指示を出す場面を考えてみましょう。上司が直属の部下に「あの件、メールで返信しておいてくれる」と頼んだ場合、「一を聞いて十を知る」頭の回転が早い部下は、上司の指示通りに即座に返信メールをするのは当たり前のこと。そのうえで、その上司を含む関係者各位をCCやBCCに入れ、そしてその返信メールの内容もお客さんがレスポンスしやすいような文面にするなど、その先を考えた行動を取ります。
ですが、何事も深入りは禁物、と言う言葉があります。上司一人・部下一人というのはレアケース。そうです、会社はチームで仕事を遂行していくために集まった集団です。上司の指示は様々な利害関係を考えている場合も少なくありません。あえてミスをさせて気付かせる、ということも考えているかもしれません。このような場合、先回りすることによって、上司が他の部下の育成を目的として黙っていることまで優秀な人はやり過ぎてしまう傾向にあり、不評を買うことが少なくありません。
先回りが得意な人は個人プレーに走りがち

「一を聞いて十を知る」優秀な人は、上司の頭の中を理解しているばかりか、会社の利益のこともしっかりと理解しているつもりになっているので、効率追求の動きを優先しがちになります。「効率」を重視すると、個人プレーに陥りがちになります。そもそも効率は個人的な理由である場合が多いのが特徴です。会社は「効果」を求める集団というのを忘れてはいけません。よく聞く言葉に「費用対効果」というものはありますが、「費用対効率」という指標がないのはそのためです。
人が成長するためには、ある程度のミスは目をつむって、そのミスによって本人に気付かせる、というある意味ふところの深さが必要な場面が少なくないのですね。「一を聞いて十を知る」タイプの人は、その前もって予見されるミスは未然に防ぐのが当たり前と考える傾向にありますので、個人プレーに走ってしまい、頭の回転が早く、ずれたところも一切にないにも関わらず、評価がイマイチ、ということにもなりかねません。
黙って核心をつくのも「知」

では、どうすればいいのでしょうか? 中国古典の荀子の言葉が参考になります。「言いて当たるは知なり。黙して当たるもまた知なり」です。
「はい、わかりました」の言葉の裏に、両方(言う・黙る)の行動準備を潜ませるのが賢いやり方です。「一を聞いて十を知る」ことができたとしても、それを一切表には出さずに、利害関係者の調整に回るのが賢い立ち居振る舞いだと言えます。
ある事柄について詳しく知っているとそれを披露したくなるのが人の心情というものです。ただし華僑は、それを得意になって披露するようなことは利口なやり方ではない、というのをよく知っています。上で紹介した荀子の言葉の真の意味を理解しているからです。
マニアの世界は奥が深く、底がないのではないか、というくらい深いのは皆さんご存知の通りですが、マニアックな話というのは、それに興味のない人にとっては苦痛以外のなにものでもないでしょう。誰しもマニアの人にそのマニアックな話を延々と聞かされた経験があるのではないでしょうか?
実は「一を聞いて十を知る」は一歩間違うと、それと同じような状況に陥る可能性があるのです。団塊の世代の方達が活躍した時代の日本においては、多少面倒だなと思うような話でも我慢していれば、今日より明日、今年より来年はさらに良くなるという確信が皆の中にありましたので、面倒なことも耐える文化が日本社会にありました。
ですが、現在は3年先を読むのも難しいくらい、生き方自体が非常に多様化された時代です。多様化された価値観をもった人たちが集う会社という集団において、「一を聞いて十を知る」ことができたからといって、それを披露してしまうと、淡々と粛々と業務を遂行したい人にとっては、マニアのマニアックな話と変わらない、と取られかねません。場合によっては、「余計なおせっかい野郎」というレッテルを貼られる危険性さえ秘めています。
10知ればまず1.5~2の対応をしてみる
「一を聞いて十を知る」人も、一部の天才を除いて大半は努力によってその頭の回転の良さを手にいれているはずですから、それを無駄にするのはもったいないと考えるでしょう。ですが、もったいないことにはなりません。聞かれた時に「いつでも答えられるようにしておく」ことによって、必ず、人知れず磨いた刀を使う時はきますので、その時まではソッと鞘の中に懐刀をしまっておくのが賢い処世術です。
と聞くと、ずっと黙っていればいいのだな、と考えるのは早計です。聞かれたことに対しては「完璧だ」と思われるような回答を用意しておけば、高い可能性で、更に突っ込んだ質問をされることになるでしょう。
「一を聞いて十を知る」という状態なのですから、指示待ち人間の人が1の指示に対して1の行動しかとらないのと比べて、まず1.5~2くらいの行動をしてみるのです。それ以上を求められている場合は、上司やその利害関係者の人が要求してきます。それに対してしっかりと回答、返答していくことによって、自分の準備万端さやお役立ち度をアピールせずとも気づいてもらうことができ、力が発揮できるようになります。
話さないことと同様に、聞かないことも重要になってきます。人は話したいことや自慢したいことは聞いてほしいと思っていますが(弱っているときは愚痴など)、必要以上に聞かれる(質問される)と警戒します。警戒されることほど、敵を作ったり、ライバルを刺激したりすることはありません。絶対に警戒をさせてはいけないのです。質問力などの書籍やセミナーなどが花盛りですが、それらも時と場合によりけりで、使い方を間違えると、必要のない警戒心を自分の周りに起こさせる愚を自ら招いてしまうことになります。
「聞かない」ことの2つの効用
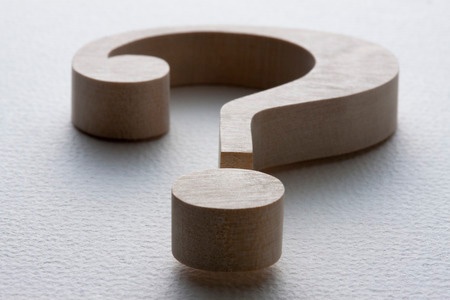
「聞かない」ことの効用がわかれば、無用な質問をせずに済むと思うので、その効用をお伝えしましょう。効用の一番目は、相手がこちらのことをバカだと思わないという効用です。ただそのためには、質問をしないまでも、あなたの考えていることを知っていますよ、わかっていますよ、というのを匂わせることが必要です。ここでのポイントは、あくまでも匂わせる、です。直接言ってしまうとそれが原因でトラブルを招いてしまう可能性がありますし、前述のように警戒されるようになります。
匂わせる方法はいろいろとありますが、華僑がよく使う手は、2、3割話して「あっ、そう言えば」と全く違う話をする、という方法です。3割が限界です。これ以上話してしまうと完全に相手は知っている、と思って次の手を考えてきます。
こうする意図は、牽制機能です。牽制はとても大切です。野球のピッチャーもバッターへの投球もさることながら、牽制球の良し悪しでチーム全体の勝ち負けに大きく左右するのは有名な話ですね。
「聞かない」ことの二番目の効用は、相手や周りを安心させる、ということです。会話にのぼっていること以外に私は興味がありません、ということが伝われば相手は安心します。安心したところを狙うのも上級者にはいい方法でしょう。そうでない方も、相手が安心した状態で自分に接してくれるのは気分がいいとまではいかなくても、余分なストレスを感じずにコミュニケーションをとることができます。
「話す」にあたっては言葉の意味を吟味する
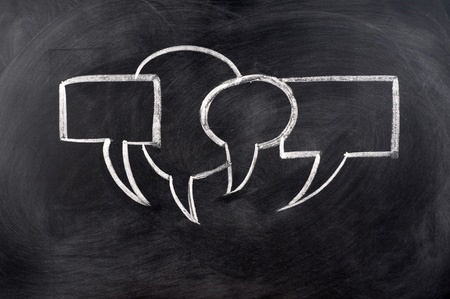
話さない、質問しない、といってもすべてにおいて、だんまりを決め込む必要はありません。例えば、営業の人が自社商品のアピールをするのではなく、他社情報や業界情報をしっかりと話すことができれば、お客さんも上司も「しっかりとわかっている人だな」と安心してもらうことができます。他社情報や業界情報をしっかりと理解しているということを話すだけであって、悪口や悲観論を語ってはいけません。目的は、無知ではない、しっかりとした人間ですよ、というさりげないアピールですから、そこでは良し悪しを語る必要はないのです。
華僑たちが異国の地で活躍するためのズルさを上手く使える理由として考えられるのが、1つひとつの言葉の意味をしっかりと吟味している、ということです。異国の地で言葉が不自由な中で生活をし、ビジネスを行うにあたって、その国その国の言葉を考えることをとても大切にしています。
例えば、日本の落語などで出てくる「女房と畳は新しい方がいい」というものがありますが、日本人の方が幸せでない解釈をしていることに気付かされます。現代の日本において畳を変える場面というのは減ってきましたが、畳を変えるときというのは、表面の井草の部分を貼りかえたり、裏返したりします。畳の本体を交換することは非常に珍しいケースです。古くなった女房と別れて、新しい奥さんにするという意味ではなく、家事や出産などで所帯じみてきた奥さんに新しい服などを買ってあげて新婚当初のように綺麗にしてあげる、というのが華僑的解釈になります。
このあたりは「女房とワインは古いほどよい」のフランス人に近いですね。東洋人でありながら西洋人的なものの見方もできるあたりが、グローバルに活躍できる思考の1つの表れかもしれません。
中国人社会では、「賢い=ずるい」「ずるい=賢い」と表現されることが多くあります。逆に中国人にあの人は「いい人だ」と言われて喜んではいけません。その意味は「あの人は単純だ」と皮肉られている可能性が高いです。
華僑たちは異国の地でうまくやっていくために狡さを知りつつ、それを使わない。あるいは少しだけ周りの幸せの為に使ってみる。そういう考え方が根底にあり、ビジネス上手と言われるようになっていくのです。部分正解と全体正解を混同しない思考がそこにはあるのですね。「質問力を磨きましょう」と聞くと、すべて質問してしまう、というのは部分正解を全体正解と勘違いしてしまっている事例としては非常にわかりやすいですね。
「会社のためのダメ出し」に上司からダメ出し

それでは“ずるゆるマスター”の事例をみてみましょう。
雑貨卸会社に勤める企画部課長補佐のRさん。部内の皆から人気の“ずるゆるマスター”の課長Yさんの部下でもあります。Rさんは学生時代に「頭の回転が早い」と仲間内で評判だったのが、自分の心のよりどころでもあります。「俺は頭の回転が早すぎるんだ、周りの人が気付かないこともなんでも気づける」。Rさん本人の自己評価とは裏腹に、社内での評価は中の上あたり。本人が納得いかないのも頷けます、自己評価通りに考えれば。
企画部という仕事柄、勤務中以外も様々な本を読んだり、ネットで調べたり、流行りの店に行ってみたりと、新しい企画のヒントになりそうなことはなんでも貪欲に吸収しようと日夜努力をしています。そのような努力を継続しているわけですから、部内での新企画プレゼンテーション会で他の社員が斬新なアイデアのように発表していても、ただの思いつきに過ぎないと考え、会社のためと思っていつもしっかりと指摘してきました。
愛社精神が強いRさんは、上司Yさんが働きやすいようにと他のメンバーのミスも事前に見抜き、訂正を促します。まるでビジネスマンのお手本のような動きをするので、それらをRさんの特徴としてあげる人は多くいます。
「どうしてわからないのかなあ、ひょっとして真剣に考えていないのかなあ」。
今日も企画会議のあと、Rさんはブツブツと独り言を言いながら会議室を後にしました。「納得がいかない、みんな本気であんなことを言っているのかな? やり手のY課長もなぜ、あんなどうでもいい企画を真面目に聞いているのかが理解できない。今度、直接Y課長に聞いてみよう」。
「Y課長、少しご相談があるのでお時間ちょっとよろしいでしょうか?」
「おお、R君。どうしたの? 怒っているの? 少し待ってくれる? T君の例の企画案を見せてもらってからでいいかな。じゃあ会議室に1時間後ね」
「はい」と言ったものの、心の中では「えっ? T君の企画? さっきの会議であの企画案のダメなところは僕が全部指摘したのに。改善の余地なしだし、その根拠も示したよ。Y課長もなぜこんな時間の無駄遣いをするんだろう」
1時間後。「R君、お待たせ。話ってなんだい?」
「Y課長、色々と申し上げたいことがあるのですが、まずですね、会議の時間が長いように感じます。皆が発表するプレゼンはそれぞれの持ち時間が20分ですが、最初の5分も聞けば、何が言いたいのかわかります。それどころか、資料をメールで流すだけで理解できるものがほとんどですので、そのような運営はできないものでしょうか?」
「ほ、さすがR君だね、最初の5分で何を話すのかを全部わかるとは。それは恐らく発表者の企画意図が5分でわかる、という意味だよね。でもその企画意図にたどり着いた思考プロセスまでは見えないのじゃないかな?」
「いえ、だいたいの思考プロセスも見えます。それに採用されない企画の思考プロセスを知ったところで、何のメリットもありません」
「なるほどなるほど。R君の意見、考え方は採用されない企画については思考プロセスを知る必要はない、と。R君は課長補佐なので、いずれは課長になるつもりだと思うけど、課長になったときに部下のみんなをどのように指導して、成長してもらうつもりだい?」
「Y課長は尊敬しておりますので正直にお伝えします。頭の回転の問題だと思うのです。それは生まれつきというほど、私も自意識過剰ではありません。普段からそれなりの努力研鑽をしていないとちゃんとした企画は出てこないと思うのです。会社は結果がすべてですから、結果がでるようなプライベートの時間の過ごし方を考えるべきだと教えます」
「もうわかった」は可能性を封じることに
「なるほど、R君の考え方はわかった。じゃあ、もう行っていいかな」
「えっ、課長待ってください、話は途中です」
「わかってくれたかい? R君がしていることはこういうことなんだ。相手の言いたいことはわかった、だからもうそれ以上、その人の話を聞く必要はない、という態度になってしまっているんだよ」
「そうですね、理解できました。そこは改めます。ですが、言い過ぎかもしれませんが、彼ら彼女らの提案は稚拙に感じることが多くあります。会議の効率化を考えても良くないと思うのですが」
「それはR君にとっての効率だよね。会社にとっての効率だろうか? 会社は効率を徹底するために集団で動いているわけではないんだよ。3年先、5年先、10年先につながるような行動が求められているんだ。その中に当然、若い仲間や新しく部署が変わって慣れない人に幅広く業務を理解してもらって、将来的に会社に貢献してもらえるようにすることもとても大切なことなんだよ」
「おっしゃる通りです。ではY課長、私は今後どうすればいいのでしょうか? 課長は私の心をすべてお見通しなのですね、なんか恥ずかしいです」
「あえて黙する」を覚えれば、飛躍できる
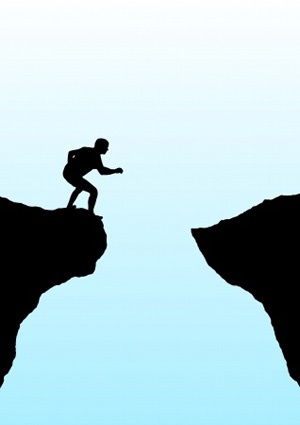
「さすがR君、頭の回転が早いね。人が自分のことをすべてお見通しと分かれば、恥ずかしい気持ちになったり、やるせない気持ちになったりするよね。まずはそれをやめてみようか。5分で企画意図がわかったとしても、ハイハイそれはわかってるよ、というのをやめてみるだけでR君は仕事ができるのだから尊敬の対象になると思うよ、しっかりと話を聞いてくれる人だって」
「とても恥ずかしいです、今日は午後から有給をいただいて明日から出直します」
「R君、そんなことしたら、みんなが君のことをまた警戒するよ。みんなの今までの気持ちを理解するためにも、今日1日午後からも頑張って会社で仕事をしたらどうかな」
「はい、かしこまりました」
あの面談から3カ月が過ぎた現在、Rさんは気付いたからといってすぐにそれを制止したりするのではなく、しっかりと話を聞く皆から好かれる課長補佐になっています。
“ずるゆるマスター”のYさんは、最初からRさんの言いたいことのほとんどを理解していました。ですが、それをすぐに指摘するのではなく、自分で気付かせることによって、自分で気付くことの大切さを授けました。また、知っているからといって、それをダイレクトに相手に伝えるのは得策ではない場合も多くある、ということを理解してもらうことにも成功しました。
あなたの周りにいるあの人も、実はすべてを知っているにも関わらず、それには触れないだけかもしれません、あなたが警戒しないために。それは何も社内に限った話ではありません。お客さんも配偶者も親も子もみな、“ずるゆる”を学んでいる人は黙って知らないふりをしているだけかもしれませんね。
あなたも今日から華僑“ずるゆるマスター”の座右の銘の1つ「言いて当たるは知なり。黙して当たるもまた知なり」を実践してみてはいかがでしょうか?

登録会員記事(月150本程度)が閲覧できるほか、会員限定の機能・サービスを利用できます。
※こちらのページで日経ビジネス電子版の「有料会員」と「登録会員(無料)」の違いも紹介しています。